「えっ、お姉ちゃん……私も一緒にエレジタットに?」
メイマイとエレジタットが正式に軍事同盟を締結するための使節がメイマイを発つ数日前
メイマイ騎士団の武将兼メイドのリムは義理の姉であり今回の使節団の団長を務めるラトに一緒に行かないかと呼びかけられてきた。
「ええ。
今後共に手を携えることになるのだから、どういう人たちなのかを把握しておくのは大事でしょ。
それに、メイマイの外に出る機会なんてあなたはなかったんだし、いいチャンスだと思わない?」
確かにラトの理屈はわかる。
自分たちが同盟を結ぶ相手がどんなものかというのを知っているのは、現在のメイマイでは以前単身エレジタットに渡ったラトだけだ。
そのラトが同盟締結に太鼓判を押したのだから問題はないのだろうが、やはり一抹の不安は残る。
なにしろ同盟を結ぶ相手は世界の敵である魔族が治めている国なのだ。場合によっては周囲の国全てを敵に回すかもしれない危険な行為である。
そのためにも、この目で実際に相手国の実情を見るのはそう悪い話ではない。
ただ、リムはあくまでもメイマイの一武将であり、ラトのように外交能力が秀でているわけではない。
メイドをしていた経験からある程度の人物眼は持っているとは思っているが、同行していって役に立つかといわれたらまた別問題だ。
「でも、本当に私が一緒に行ってもいいの?私が行っても足手まといになるだけなんじゃないかって……」
「ああ、その辺は心配しないで。
交渉ごとをするのは私やいっしょに連れて行く文官たちなんだから。まあ、あなたは私たちの護衛と言ったところね。
このことに関してはティナからも許可を貰っているから問題はないわよ」
つまり、ラトの役目は文官たちの護衛ということだ。
同盟締結のために行くだけならば護衛は不要とも考えられるが、海路を取るとはいえ途中で何に出くわすか
分からない以上あるていどの護衛はやはり必要だ。
一見頼りないリムではあるが、こう見えても過去にティナやラトなどと一緒に暗黒竜を封印した実績もありメ
イマイの中では有能な武将として知れ渡っていたりする。
少なくとも、ここにいる面々の中ではラトの次に戦闘能力のある人間だ。護衛としては申し分ない。
「本当はアニ―タ達も連れて行きたかったんだけれど、ティナからダメ出しを喰らっちゃってね。
『そんなにゾロゾロ将軍連れて行ってどうするのよ!』ってお冠喰らっちゃったわ」
アニ―タとはラトやリムと同じメイマイの女性将軍のことだ。確かにそんなにいっぱい将軍を引き抜いて出発されたらいざというときにティナも困るだろう。
「ま、そういうことだからせっかくの機会を楽しみなさいな。あなたは今まで自分のために、っていうことなかったでしょ。
今回ばかりは仕事とか任務なんて忘れて、知らない世界をその目で見てきなさいな」
ラトはまるでリムを労るかのようにリムの肩をぽんぽんと叩いた。
どうやらラトの真意は護衛とかなんとかではなく、純粋にリムに外の世界を見せてゆっくりしてもらいたいというもののようだ。
「お姉ちゃん……」
あくまでもリム本人のことを想っての誘いということにリムは胸の奥が熱くなった。義理の姉妹のはずなのだが、まるで本当の姉のように思えてくる。
「ありがとうお姉ちゃん!本当にありがとう!じゃあ私、早速準備してくるね!!」
その顔の満面に笑顔を浮かべたリムは、ラトに手を振りながら自分の部屋へパタパタと戻っていった。
妹が喜び駆けていく様をラトも笑顔で見送り、完全に見えなくなった後に低い声で呟いた。
「…ええ。しっかりと準備してきなさい。その体の隅々まで磨き上げてね。
そして向こうで見せてあげる。あなたの知らない、素晴らしい世界をね……うふふ…」
まるで感情を抑えるように俯き気味に笑うラトの瞳は、本来の藤色ではなく不気味な赤色に輝いていた。

☆
エレジタットでの同盟の調印式は特に大きなトラブルもなく粛々と行われた。
リムは一応護衛役という肩書きで使節団に加わっていたので調印式ではラトの後方に控えていたのだが
一見メイド姿のリムは護衛というよりもラト付きのメイドにしか見えない。まあ護衛に見えないという点はいざというときに有利かもしれないが。
もっとも、リムが手を出す場面がでることもなく、最後はラトとエレジタット君主ルドーラが手を取り合って
メイマイとエレジタットの軍事同盟は無事に締結の目を見ることになった。
これは、2国が挟む大国プリエスタがどちらかの国に侵攻して来た時、攻め込まれたほうを助けることで
2国間の関係を強調させ、プリエスタの領土的野心を抑えることを目的にした同盟である。
正直、メイマイもエレジタットも国力ではプリエスタに単独で立ち向かうのはかなり難しいと言わざるを得ず
その点からではこの同盟を結ぶ意義は十分にあるといえる。
調印式の後、リムは宛がわれた部屋へと戻ったが、そこにさっきまで調印式の主役を勤めていたラトが入ってきた。
「いやー、疲れたわ。やっぱ慣れないことはするものじゃないわね。
でも、これでメイマイの無事も確保されたわ。ここまで来たかいがあったというものよ」
「うん……」
ラトは大役を果たしたということですこぶる上機嫌のようだが、リムの方はどこか浮かない顔をしていた。
「うん?どうしたのよリム。もしかして、長旅で疲れたとか?」
「ううん、そんなことない…。ただ、ここのお城の雰囲気が……」
リムが数日に渡る船旅の後にエレジタットについた時、最初に感じたのは『虚無』だった。
とにかくこの地には生き物を殆ど感じない。荒涼たる岩地が視界一杯に広がり、人間はおろか鳥や小動物の気配さえ感じない。
いや、植物すら目に入ってこない。
こんなところで国家としての形を維持できるのかと思っていたら、エレジタットには君主ルドーラとルドーラに仕える
直属の魔族以外に住民はいないとラトが教えてくれた。
エレジタットの兵隊は国内に数ヶ所あるプラントで作られる魔法生物で、寿命が短い代わりに
短期間で無尽蔵に生産できるから必要な時以外は兵隊すら置いていないらしい。
つまり、このエレジタットという国は生産力を持たない土地が国土の殆どを占め、国民はルドーラと
数十人の魔族しかいないという普通に考えたらとても国家とは呼べない規模の代物なのだ。
いや、ひょっとしたらこの国で『生きている』ものはルドーラたち以外いないのかもしれない。
リムが感じた虚無もそこからきているのだろう。
(この国はどこかおかしい)
ラトがいる手前口には出せないが、リムはこの国を見てそう感じていた。
ルドーラは傍目で見て実に紳士的だったし、自分たちを接待してくれた魔族も意外といってはなんだが親切に接してくれた。
ただ、その好意的な態度がなにかひどくよそよそしく感じられるのだ。
本当に上辺だけ、表面だけの優しさという風に感じられ胸の奥が吐きそうな嫌な感覚に襲われてくるのだ。
「ねえ、お姉ちゃん…。本当にこの国と同盟を結んでよかったのかな…」
何故かリムは、エレジタットと手を組むことでメイマイにとって取り返しのつかない事態が起こるような気がしてならなかった。
そう感じさせるだけの空気がこの国と君主のルドーラには漂っている。
「?今さら何言っているのよ。いいに決まっているじゃない。これでメイマイの平和が保てるんだから」
「ううん…。この同盟、きっとメイマイによくないことが起こる……。今からでも取り消した方がいいかもしれない…」
ラトが前々から主張している『エレジタットと手を組めばメイマイの平和が保てる』という言葉が、リムにはもう信じることが出来なくなっていた。
ラトがこの国にそれほどの信頼を置けているのがリムには理解できなかった。
自分が言うのもなんだが姉は物事の正邪を見抜くことは随一だと思っている。その姉がこの国に漂う邪な気配を感じないわけがない。
「ふぅん……。リムはそんな風に考えているんだ。私がウソを言ってると思っているんだ……」
「え?!そ、そんなことはないけど……」
自分が信用されていないと感じたのか不機嫌そうに自分を睨んでくるラトに、リムは慌てて手を振りながら否定してみた。
が、本心はまさにその通りなのであんまり説得力が感じられない。
「…………」
リムを睨むラトの目には冷たい悪意すら感じられてくる。ここまで敵意をもった視線をラトから向けられたことがなかったリムはゾッと肩を振るわせた。
「お、お姉ちゃ……」
「ま、いいわ。そういうことにしておいてあげる。
それに、肝心なことを言い忘れていたのを思い出したわ。そのためにここに来たんだしね」
ぶるぶると脅えるリムの姿に軽く笑いながら、ラトはスッとその場から立ち上がった。
そう言えば、ラトがなんでリムの部屋に入ってきたのかを聞いてなかった。
最初は単に顔を見せるために入ってきたのかと思っていたが、どうやら違うようだ。
「リム、これから本当の調印式が行われるからすぐに支度をなさい」
「本当の……、調印式?」
リムは最初ラトが何を言っているのか理解できなかった。調印式は既に先ほど滞りなく終了したはずだ。
それなのに、その後にまた調印式が行われるなんて聞いたことがない。
「なに、それ……。お姉ちゃん、私、そんなこと聞いてない……」
「そりゃ聞いてないわよ。多分、使節団の誰も知らないんじゃないかしら。でも調印式はこれから行われるわ。
とっても、とっても愉しい調印式がね……」
リムを見下ろすラトが、何故か酷く恐ろしいものに見える。目の前にいるのははたして本物の姉なのか、リムにはわからなくなっていた。
「い、いいよお姉ちゃん……。私、気分が悪いからここで寝てる……
ど、どうせ自分が言っても大して役に立たないし……」
まるでラトから逃げるように後ずさりしながら、リムは精一杯の笑顔を浮かべてベッドの中に潜り込もうとした。
が、その手をラトががっしりと掴んできた。
「ダメよ。リムも出なさい。ていうか、リムが出ないと困るのよ。
何しろ、この調印式の主役はあなたなんだから……」
リムを掴むラトの手には物凄い力が込められている。いざとなったら腕ずくでもリムを連れ出すという意思が込められているようだ。
「いやっ!放してお姉ちゃん!痛い、痛いよぉ!!」
先ほどまでとガラリと雰囲気が変わったラトにリムは心底恐怖を覚えた。
明らかに姉は自分の知っているいつもの姉じゃない。まるでこのエレジタットの放っている毒気に侵されているかのようにリムには感じられた。
「私が主役?!何を言ってるのお姉ちゃん!!一体、私に何をさせる気なの?!ねえ!!」
「あなたのその体で、メイマイの忠誠心をルドーラ様に示すのよ。魔力に溢れたあなたなら、ルドーラ様もきっとご満足してくださるわ……」
まるでルドーラが自分の主であるかのように語り、口元を釣り上げて笑っているラトの瞳はいつの間にか爛々と赤く輝いていた。
「ひっ?!」
まるで魔族のような赤い瞳を見せられて、リムの恐怖のタガは一気に外れた。
目の前の姉は明らかに『ちがうもの』になっている。このまま姉に連れて行かれるともう二度と戻ってこられない!
「い、いやああぁぁぁぁっ!!」
「さっきからうるさいわねぇ……。少し大人しくしなさい」
恐怖のあまりじたばた暴れるリムに業を煮やしたのか、ラトの瞳がギラッと赤い光を放った。
赤い光は正確にラトの網膜を焼き、視神経を通してラトの脳髄に染みこんでいく。
「ひぁっ!あ………」
ラトの瞳が不気味に光ったのを目にしたリムの瞳も一瞬赤く輝き、その直後頭の奥がキーンと痺れるような感触がリムを襲い
リムの視界は強烈な眠気と共に見る見るうちに真っ暗にぼやけていった。
「お、おねえ、ちゃ……」
自分の胸にくたくたと崩れて意識を失ったリムに、ラトは目をニタニタと歪めながらその頬を撫で回した。
「うふふ、ゆっくり眠っていなさい。眠っているうちに、全ての用意を整えてあげるから…」
ラトはそのままリムを抱え上げ、コツコツと足音を立てながら部屋を後にしていった。
ラトの手の中で、意識がないはずのリムの瞳から一筋の涙がこぼれ、床に印を残していっていた。
☆
(ん………?)
まだまどろみの中にある意識で、リムは自分の体の違和感におぼろげに気がついた。
(あれ…?なんか体がスースーする……。それに、なんかあちこちがひっぱられて……?
これは一体なんなんだろう。自分は確かお姉ちゃんと一緒にいて、それから、それから………?!)
リムの頭に、自分の身に起こった恐ろしい記憶がまざまざと蘇ってくる。
そうだ。自分は様子がおかしくなった姉さんの光った眼を見てからいきなりとっても眠くなって、そのまま……
「はっ!!」
ぐわっと意識が覚醒したリムはかっと目を見開き、自分がどうなっているのかを確かめようとした前に…
目の前の光景に目を奪われてしまった。
リムの周りには一緒にメイマイから来た使節団の面々が揃っていた。
ただし、そこにいる全員が裸に剥かれ纏わりついてきている女魔族と肉の饗宴に明け暮れている。
ある者は魔族に跨られ、ゆっさゆっさと腰を揺すられながら中にドクドクと精を搾り取られ
ある者は四つん這いになった魔族を後ろから貫き、快楽に顔を蕩かせて肉欲に溺れ
ある女性は腰から逸物を生やした魔族に犯され、よがり声を上げながら潮を吹き上げ
ある女性は前と後ろから挟み撃ちにされ、口と膣内に延々とスペルマを流し込まれている。
それは爛れきった魔宴の真っ最中であった。
リムの周りに広がる空間全てがムワッと咽かえるような淫気に侵され、中にいる人間全てを淫辱に狂わせていた。
「な、なに……?!なにこれ、なんなの……。みんな、どうしちゃったのよぉ……」
まだ色事への関心をそれほどもっていなかったリムにこの光景はあまりにも刺激が強すぎた。
まともに物事を考えることが億劫になり、蠢く肢体、喘ぐ嬌声、甘酸っぱい体液の香り等々、五感に直接訴えてくるものが
脳内にダイレクトに飛び込んでくる。
決して自分がされているわけではないのに、まるで自分の体が責められているような、そんな錯覚すら覚えてしまう。
(や、やだ……。こんなの見たくないのに、ないのに目が……離せない……!)
そんなリムも漂う淫気に当てられてしまったのか、胸の奥がカッと熱くなり心臓の鼓動が耳で聞こえるくらい大きく激しくなってきている。
火照った体がすきま風で冷やされ、少し肌寒く感じられる。
そこで初めて、リムは自身が一糸も纏わない姿だということに気がついた。
「えっ?!や、やだっ!」
慌ててリムは手で自分の大事なところを覆い隠そうとするが、腕は上に向いたまま全然言うことを聞かない。
見ると、腕は天井から下がっている鎖に縛られ、両足には見るからに重い鉄球が取り付けられた足かせを嵌められている。
要するに、リムは全裸で全く身動きが出来ない状態にされているということだ。
「な、なんなのこれ!!私、なにをされてるの?!やだやだやだぁぁ!!」
自分に何が起こっているのか全くわからず、リムはパニックになって懸命に体を揺すってここから逃れようとした。
だが、手かせ足かせはもちろんびくともせず、薄暗い部屋の中で白い裸体が扇情的に体をくねらせているようにしか見えない。
リムは無意識ではあるが、見るものが見たら酷く欲情しそうな姿を暫く晒し続けていた。
いや、それを見て実際に欲情しているものがいた。
「うふふ…リム……。本当の調印式にようこそ……」
わぁわぁと泣き叫ぶリムの耳に聞き覚えのある声が聞こえてきた。
それはいつも自分の傍にいて、自分のことを守ってくれたとっても優しくとっても頼もしい……
「お、お姉ちゃ……!!」
助かった!と一瞬リムは思い…、次の瞬間絶望した。
いま自分がこんな目にあっているのは間違いなくその『お姉ちゃん』のせいなのだ。
つまり、この状況でラトが出てきても決して事態は好転しない。むしろ悪化する可能性すらある。
そして、残念ながらリムの懸念は杞憂ではなかった。
「あらぁ……、どうしたのリム…。そんなに脅えた顔しちゃって……」
甘ったるい声を出しながらエレジタット君主ルドーラにしなだれかかりながらリムの前に現れたラトを見て、リムは一瞬それがラトだと認識できなかった。
それほどラトは先ほどとは容姿を一変させていた。
着ているものはいつもの拳法着ではなく、非常に露出が高い砂漠地帯のハーレム衣装のような衣服をまとっており
外気に当てられている地肌が全身がうっすらと赤く上気している。
瞳は先ほど最後に見たとき同様本来の藤色ではなく赤く変化し、寝ぼけているかのようにどんよりと濁っている。
そしてなにより、伸ばした揉み上げの間からはまるでエルフ族のような長い耳が収まりきらずに顔を覗かせていた。
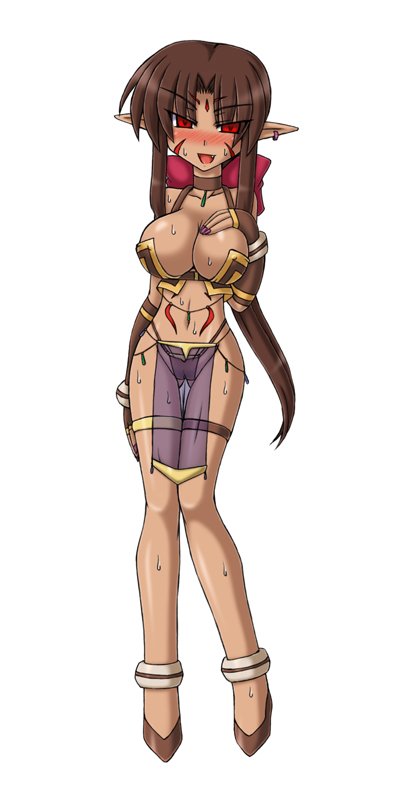
「…お、姉ちゃ……ん?何、その姿……。まるで、魔ぞ……」
そう、その姿はこれまでリムが城内で目撃し、今回りで使節団と肌を重ねあっている魔族そのものであった。
そのあまりにも印象の違う姿に、もしかしたら目の前の姉は偽者で自分はこの偽姉に騙されていたのかもしれない、という
淡い期待が少しだけリムの心に浮かび上がった。
だが、ちょっとだけ輝いたリムの顔を見たラトは、その希望を打ち消すかのように低く微笑んだ。
「ふふっ、リム…。あなた私がニセモノのお姉ちゃん…、なんて考えているんじゃないの?
お生憎様。私は正真正銘、あなたの『お姉ちゃん』よ。もっとも、人間はやめちゃったけどね……
この新しい体ね、ルドーラ様が私にくださったのよ。ルドーラ様にお仕えするに相応しい、素晴らしい『しもべ』の体を…
どう?とっても綺麗でしょ?」
「お、お姉ちゃ……人間やめたって、ウ、ウソ……ウソでしょ……」
ラトはリムに見せ付けるかのように殆ど素裸といっていい肢体をいやらしく蠢かせていた。
敬愛する姉がそんな姿を見せるのもショックであれば、人外に化生していたのも非常なショックだった。
「ウソじゃないわ。もう私の体は魂どころか髪の毛一本までルドーラ様のもの。
それよりも、周りを見なさいな。この素晴らしい、背徳と快楽に満ちた堕落の調印式を……」
背徳と快楽、ラトに改めて言われるまでもない眼前に広がる光景。これのどこが調印式というのだろうか。
「ここにいるメイマイの人間の、男も女も全て私たちしもべの体が与える快感に酔い狂わされているわ。
その快感はその人間の意思を奪い、私たちの快感なしでは生きられない体へとなっていくの。
その結果、私たちの命令を素直に聞く操り人形になる…
そして、この人間たちはメイマイを冥府兵団の思い通りに動かすためのコマに変わるのよ!
メイマイを戦禍に引きずり込んで、ルドーラ様の目的を叶えるためにね!アハハハ!!」
つまり、ルドーラは最初からメイマイと対等な軍事同盟を結ぶ気はなく、メイマイを影から操って
自分の思い通りに動かして労せずに強力な軍隊を手に入れようと画策したというわけだ。
しかも、その陰謀に姉のラトが一枚かんでいた。女王ティナの親友で信頼も厚く、メイマイの筆頭武将であった姉が
まさかメイマイを裏切っていたなんて!
「そしてリム、さっきも言ったとおり今日の調印式の主役はあなた!
その純潔と魔力をルドーラ様に捧げ、あなたもルドーラ様のしもべに生まれ変わるのよ!」
ラトの横にいたルドーラが、全身についた目をギョロギョロと動かしながらリムに向って近づいてきた。
ルドーラの顔には、昼間の調印式の時には見せていなかった好色そうな笑みが張り付き、リムの体をまるで物色するかのようにまじまじと眺めている。
上へ下へ、舐めるようにリムの体を観察したルドーラは、不意に不満そうに眉を顰めラトを睨みつけた。
「ふむ……、お前に比べたら随分と貧弱な体をしていますが、これで私への供物になるのですか?」
「も、申し訳ありません…。ティナめが熟れ頃の女を連れ出すのを許可しなかったので、仕方なく私の手で連れ出せる中で
一番マシな物を用意した次第でございます…
あ、でも体は貧相でも魔力は相当な資質を秘めていますので、きっとルドーラ様も満足されるかと…!」
不機嫌になったルドーラに顔を青ざめたラトは、まるでリムをお得な品物のように言い繕ってなんとかルドーラの歓心を買おうとした。
そのかいあってルドーラの機嫌は幾分持ち直したが、今度はリムの方が大きなショックを受けていた。
「え……、お姉ちゃん……?お姉ちゃんが私を連れてきたのって、外の世界を見せるためじゃなかったの……?」
何しろ今のラトの言い分では、まるでリムをルドーラに捧げるためにエレジタットに連れて来たとしか解釈できない。
しかも、その物言いからはリムに対する愛情も何も感じられるものはない。まるで単なる荷物のような扱いでしかないように感じられる。
ラトが自分のことをそんな風に思っていたなんてリムには到底信じられず、今のラトの言葉も受け入れられるものではなかった。
だから、なんとしても聞きたかった。自分の耳で、ラトが冗談だって言ってくれることを。
「ねえ、お姉ちゃん…。ウソなんでしょ?!今言ったこと、全部ただの冗談なんでしょ?ねえったらぁ!!」
「………」
だがやはり、リムを見るラトの目線は妹に対するものではなく、むしろ悪意すら感じられるものだった。
「ピィピィうるさいわねぇ…、今言ったでしょ。
あなたはメイマイがエレジタットに忠誠を示すための捧げ物。ルドーラ様を満足させるための肉壷。
そうでなければ、なんであんたみたいな泣き虫の役立たずをわざわざここまで連れてきたりするのよ」
それはラトの秘めた本心なのだろうか、それともルドーラによって作り変えられた心と体が言わせたものなのだろうか。
とにかく、そこにはリムへの想いなど一片たりとも感じられるものはなかった。
そしてそれは、純粋なリムの心を折るには充分過ぎるものだった。
「う、うそよね……?お姉ちゃんがそんなこと思っているわけ、ない……。だって、姉妹でしょ?ねえ、お姉ちゃん!!」
「…所詮私とあなたは血は繋がっていないわ。私のことを慕ってくれて少しいい気分にはなれたけど、度が過ぎると鬱陶しいのよ。
いっつもいっつもお姉ちゃんお姉ちゃんって纏わりついて……、正直、消えてほしいと思ったときもあったわ」
ラトは悪意に満ち満ちた目を向けてリムを詰り続けている。そこには、演技や上辺といったものは全く感じられない。
つまり、これは紛う事なきラトの本心なのだろう。ルドーラの手で相当に捻じ曲げられたものであったとしても。
「でもね……」
だが、そこまで言ってラトは突然好色そうに顔を歪ませた。口からちょろっと飛び出した赤い舌が、いやらしそうに唇を舐めている。
「そのまだ青々とした育ち盛りの体を押し付けられるたびに、なんか間違いを犯しそうになる思いもしばしばあったのよ。
特に、この体になってからは襲いたくなる気持ちを抑えるのに大変だったんだから…」
リムを見るラトの眼は、横にいるルドーラと同じものになっている。
すなわち、リムを肉欲の対象として捉えている目だ。
「うふふっ、まだ男なんて咥えたこともない、全く穢れを知らない体…
でもそれじゃあルドーラ様を受け入れるのは難しいでしょうから……、まずはお姉ちゃんがあなたの体を目覚めさせてあげるわ。
あなたが全然知らない、素晴らしい世界に導いてあげる……」
内から湧き出す興奮を抑えきれず、潤みだした股の間をくにくにと弄りながらラトはまるで食事にありつく肉食獣のようにリムに近づいてきた。
「ひっ、や、やだぁっ!来ないでぇぇ!!むぐぅっ!!」
最早目の前のラトを姉ではなく自分を狙う魔族としてしか認識できなくなっていたリムは、じりじりと近づくラトに体を捩って抵抗したが
広げた両手で挟まれて動きを封じられた直後にラトの唇がリムの唇をちゅうぅっと塞いできた。
突然の、そして初めてのキス。しかもその相手が姉と慕っていた女性ということでリムは目を白黒させて抵抗らしい抵抗をすることも忘れてしまった。
それを幸いに、ラトは一気にリムの口内に舌を突っ込み口腔を蹂躙すると共に、唾液をとろとろとリムの口に注ぎこんでいった。
唾液が流れていくところはまるでお酒でも口に含んだかのようにカッと熱くなり、喉の奥が燃え上がってくるような不思議な感覚に襲われてきた。
「んぅぅ……んふっ……」
「んーっ!!んーっ!!」
その熱さに耐えかねて唾液を吐き出そうにも、口がピッタリと重なっている上に顔を両手で押さえ込まれているので
首を動かすことすらままならず、反対にラトの責めはますます大胆になっていく。
滑る舌が独立した生き物のようにリムの舌を捕らえ、くちくちと粘ついた水音を立てて舐り尽くし、扁桃腺の奥までずるずると伸びて蹂躙していく。
喉が舌で舐められるという予想も想像も出来ない感覚にリムは快楽を感じるよりも不快感が先に立ち、苦しそうに眉を顰めた。
「ん………?」
目の前のリムが蕩けるどころか不快感を露わにしていることに気づいたラトは、チュルッと唇を離すと困った顔をしてリムに囁いた。
「どうしたの、リム?気持ちよくないの?せっかくお姉ちゃんがリムを気持ちよくさせようとしているのに、そんな顔しないでちょうだいよぉ…」
「や、やだ……。そんなの、全然気持ちよくないぃ……。お姉ちゃん…、正気に戻ってぇ……!」
目に涙を浮かべて懇願してくるリムの顔に、快感に溺れている気配は微塵も感じられない。
これはラトには予想もつかない展開だった。自分の責めでリムをとろとろに蕩かして、ルドーラ様が強制進化を行う前の
露払いを務めるはずだったのに、リムは悦ぶどころか完全に嫌がっている。
「なんで……?なんで、気持ちよくならないのよリム!あんたもしかして不感症なの?!ねえ!!」
このままではルドーラ様の役に立てない。あせったラトは別方向からの責めを考え、まだ膨らみと言うのもおこがましいリムの胸を
両手でギュッギュッ!と揉みしだき、親指と人差し指で蕾のような乳首をぐりぐりと押し潰した。
自分がルドーラに胸を愛撫された時には爪先から脳天に突き抜けるくらいの快感がビリビリと走っていったから
ここをいじくればリムも快感に目覚めるだろうという考えからだった。
が、丹念に揉みこむもののリムの顔は一向に蕩けはじめない。
むしろ、歯を食いしばって痛みに耐えているように見える。
「い、痛いの……!痛いのお姉ちゃん!そんなにおっぱい搾らないでぇぇ!!ちぎれちゃうよぉぉ!!」
「ど、どうしてよ……。こんなにしっかり揉んでるのに、どうして気持ちよくなってくれないの!!」
自分がどんなに気持ちよくさせようとしても、リムはその体を肉欲に支配されたりせずに抵抗してくる。
なぜなのだろう。本当にリムは不感症なのだろうか。それとも自分にはない快楽に抵抗できる術があったりするのだろうか。
「…認めない……。そんなの認めないわ!私の手で気持ちよくならないなんて認めない!!
こうなったら、意地でもあなたを快楽の虜に堕としてみせるわ!覚悟しなさ……」
もうどうしてよいか術が分からず、とうとうキレてしまったラトの手を後ろからルドーラが仏頂面で掴み上げた。
「ル、ルドーラ様!!」
「見ていられません。人を悦ばせるということを全く理解していない。
ラト、お前は他の人間と交わった経験がまだないようですね……」
「うっ……」
図星を指されラトは言葉に詰った。
確かにラトはここで以前ルドーラに犯されるまで男性経験はまるでなく、ルドーラのしもべとなった後もエレジタットから離れるまで
ずっとルドーラ一人に肉体を開発され続けていたのだ。
しかも、メイマイに戻った後は正体が発覚するのを警戒して一度も人間の擬態を解いたことはなく、他の人間を襲うこともなかった。
つまり、ラトには他人がどうすれば感じるかということに対する経験が全く不足していた。
自分がどうすれば感じるかというのはルドーラとの性交で十二分に承知していたが、そうだからといって
他人が同じ事をされて感じるかというのはまた話が異なる。
いや、ラト本人はそのようにしていると思っていても、実はまったく出来ていないということもありえた。
むしろそうだからこそ、リムが快楽よりも苦痛をより多く感じているのだと思われる。
「しかたがありません。ここはお前にも少し教育を施す必要があるようですね……
メディーナ、来なさい」
ルドーラは使節団と多数のしもべが交わっている方へと顔を向け、一人のしもべの名前を呼んだ。
すると、許容量をとうに超えた快楽で息も絶え絶えになっている男に騎乗位で跨っていたしもべがゆっくりと立ち上がると
まだ股下から精液を滴らせたままこちらへと歩いてきた。
メディーナと呼ばれたしもべは、ほかにルドーラが侍らせているしもべに比べて長身痩躯で大人びており、かけている
少し度の強いメガネから知的な印象を与えてくる。
が、メガネの奥の赤い瞳には他のしもべと同じくルドーラに盲従する意思と肉欲に爛れた光が宿っていた。
「んふっ、お呼びでございましょうか、ルドーラ様」
「メディーナ、そこに吊るされている供物をお前の艶技でじっくりと開発しなさい。
その際、ついでにそこにいるラトに女の悦ばせかたを教えてあげるのですよ」
「畏まりました、ルドーラ様…」
メディーナはルドーラに恭しくお辞儀をすると、顔を赤らめてリムの方へと向って来た。
ラトの責めが中断して一息ついていたリムだったが、新たに自分へと向ってくるしもべを見て息を飲んだ。
それは決して恐怖からではない。
メディーナのあまりに熟れきった大人の体に、ある種の憧れの気持ちを持ってしまったのだ。
出ているところはしっかりと飛び出し、くびれているところはきゅっと窄まっている。
胸はラトのものに比べてもさらに巨大で形も整い、それまでの情事の影響か乳首は堅くしこり先端からぷっくりと母乳を滴らせている。
まだ産毛くらいしか生えていないリムの陰部と違ってメディーナのそこはしっかりと毛で覆われ
手入れを欠かしていないのかきちんと刈り揃えられている。
その陰毛周りは受け止めた精液と吐き出した愛液でぬらぬらと光り、ムッとするような性臭を漂わせてきていた。
そのパーツの一つ一つは毒々しいまでに淫靡なのだが、それが一つにあわさるとなぜか非常に美しく感じられてくるのだ。
実はリムは幼い頃に暗黒竜の襲撃を受けて両親を失いラトの家に引き取られている。
そのため、リムには実母の記憶があまり残っておらず大人の女性というものをそれほどよく知らない。
また、自分の体が歳に比べても非常に控えめな体つきのため、ちゃんと女の体型になっている女性に無意識にコンプレックスを抱いてもいた。
それらが合わさり、今のリムに目の前のメディーナは恐ろしくもあるが非常に妖しい魅力も抱かせていたのだ。
「うふっ、これまた可愛い子……。全く性の匂いを感じさせない、瑞々しい蕾のよう…
それがもうすぐ、ルドーラ様の手で淫らに染められて大輪の花を咲かせるのね。そう考えただけで、濡れてきちゃう…」
リムを通じて自分がルドーラにしもべにされた時を思い起こしているのか、メディーナははぁはぁと息を切らしながら
グチャグチャに濡れた股間に忙しなく指を出し入れしている。
その光景に、リムのみならずラトまでもが目を奪われていた。
「んふっ…、もう少し楽しみたいけどルドーラ様のご命令もあることだし……
その体、性に目覚めさせてあげるわ…」
メディーナは指遊びに耽っていた手を股間から放すと、愛液でべとべとに濡れている指をひと舐めしてからその口をリムの乳首へとくわえ込ませた。
「んんっ!!」
乳房の先が熱く柔らかい粘膜に包まれ、リムはゾクッと背筋を軽く振るわせた。
それは、痛みと不快感しか与えられなかったラトの責めに比べると入りばなは随分とソフトな印象を受ける。
が、そう感じたのも最初だけだった。
「…っ?!いひっ!!」
メディーナの口に収まったリムの乳首がメディーナの舌でころころと転がされ始めた。
舌を使われたという意味では先ほどのラトも同様だが、ラトとは決定的に異なるところがあった。
自分のことしか考えてなかったラトの舌動きに比べ、メディーナの舌使いはリムの体を悦ばせようと
巧みに強弱を使い分け、その性感を高めようとしてきている。
ねっとりと絡みつく舌はおろか唾液までもがリムの乳首を昂ぶらせ、しゃぶられているほうばかりか
もう片方の乳首も堅くしこって猛烈な熱と疼きを呼び起こし、その熱が胸のみに収まりきらずにたちまち全身へと広がっていく。
触られているのは胸だけなのに、どうしてこんなに体が熱くなってくるのか。リムには全く理解できない。
なぜかと考えようにも、頭の中にバチバチと火花が飛びまともな思考力が働かない。
「ひっ!ひぎっ!!ひゃああぁぁ!!」
(いやぁぁ、なにこれ!体が、体が熱いですぅぅ!!)
全身を襲う未知の感覚にリムは完全に惑乱し、頭を天井が見えるくらいまで仰け反らせて悶え狂っていた。
だが、四肢を固定されたリムに逃げることはおろか身を捩じらせて快感を散らすことも出来ず、体の中に湧き上がった快感は
その密度をどんどんと増していき、ついにはリムの脳髄まで快感の炎で燃やし尽くすまでになっていった。
(あぁっ!!ダメぇ!こ、こんなにされたらわたし飛ぶ、飛んじゃう!!)
だが、どんなに快感の炎が高まっても、リムは最後の一線を越えることはなかった。
メディーナの責めはリムを高みに上らせようとはするものの、決して絶頂までは導かず生殺し状態のままひたすらリムに快感を与え続けた。
「ひ、ひぃぃっ!も、もうらめ!これ以上ぺろぺろしないでくださいぃ!これ以上されたら、私くる…狂っちゃいますぅぅ!!
やめてくださぁぁぁい!!ひひゃあぁ〜〜〜〜〜〜ぁあ!!」
その結果、終わりのやってこない快感にとうとうリムは頭のヒューズは吹き飛び、フッと目の光が消えたかと思うとそのままがっくりと気絶してしまった。
「あ…、あぁ……あひ……」
リムがもうまともな言語すら発しなくなったのを見てからメディーナはようやっとリムの乳首から口を離し
リムのあまりの乱れ様を呆然と見ていたラトにつんと言い放った。
「見なさいラトさん。
人を悦ばせるというのはこうするのです。自分のことばかり考えていては、相手は決して気持ちよくはなりません。
相手のどこが弱いのか、何をされると一番感じるのかを見極めれば、たかが乳首を弄るだけでもこのように乱れまくるのですよ」
「はぁ…」
思わずラトは生返事をしてしまったが、確かにメディーナの舌技でここまでよがり狂わされたリムを見てしまうとその言にも一理あるといわざるを得ない。
「あなたは他の人に奉仕するということをまだ理解していません。ルドーラ様しか相手がいなかったから無理もありませんがね。
ですから、この少女をルドーラ様だと思って奉仕しなさい。そうすれば、あなたの手でこの子を淫らに狂わせることが出来ますわよ…」
「リムを……ルドーラ様だと思って?」
そう言われてもラトにはピンと来ない。リムはリム、ルドーラ様はルドーラ様だ。男性と女性という
決定的な違いもあるし、どこをどうしたらリムが感じるようになるのかいまいち自信がもてない。
「…この子を悦ばそうと思ってすればいいのですよ。自分が愉しもうと思わないで、相手を愉しませるのです。いいですね」
「は、はい……」
リムを悦ばす。その一点を考えラトはリムの股間の間へと顔を動かした。
そこは直接触られていないにもかかわらず、たらたらと媚液が滴り濃厚な性の匂いを放っていた。
「リムを悦ばす…。リムを……」
まるで自分に言い聞かせようにラトは呟きながら、伸ばした舌をリムの股間の孔へとズルルッと潜り込ませた。
その感触にリムはビクッと体を震わせたが、まだ意識が戻りきっていないのか悲鳴を上げたりとか激しいリアクションは行わなかった。
先ほどまでのラトなら反応の鈍いリムに苛立ち、膣の中を無茶苦茶に嬲り尽したかもしれない。
だが、それでは何百年たっても快楽を与えることは出来ないと思い知らされたラトはとにかくリムが悦びを感じるようにすることを心がけようとした。
長く伸ばした舌がリムの中の襞一枚一枚を丁寧になぞり、こりこりと硬い肉の感触をぺろりぺろりと味わう。
膣の奥からとろとろと溢れてくる蜜を舌で掬い取り、喉へくぴくぴと流し込んでいく。
舌で前の孔を弄びつつ、後ろの孔へは指を伸ばし、閉じた蕾をほぐすかのようにつぷつぷと指で押し、細身の体から比べると
意外なほど肉付きのよい尻肉を掌でむにむにと揉みこんでいった。
「………あぅ?」
下半身からぴりぴりと湧き上がってくる心地よい肉の疼き。
その感触に飛んでいたリムの意識が半ば強引に呼び覚まされ、消えていた眼の光がスゥッと元に戻ってきた。
が、リムとしては気絶していたままの方が良かったのかもしれなかった。
覚醒したりムが目にしたのは、リムの腰に手を回し太腿の間に頭を入れているラトの姿だった。
その頭が細かく蠢くたびにピチャピチャと猫が水をのむ時のような水音が聞こえ、同時にリムの秘部からゾクゾクするような刺激が伝わってくる。
「え……?!やぁっ!お姉ちゃん!!」
自分の股間が姉に舐められていると気づくのにリムは数秒の間隔があき、気づいた時には恥ずかしさと
背徳感に顔が見る見るうちに真っ赤になっていった。
「やめてお姉ちゃん!そんなとこなめないでぇ!!」
だがリムがどんなに懇願してもラトは顔を離すことはなく、むしろさらにその舌使いを激しくしていった。
その動きは先ほどの自分本位の強引なものと違い、リムの性感をじっくりと刺激してじわじわと高みに上らせていくものだ。
ただ、それは決してリムのことを想ってのものではない。
ラトが行っているのはあくまでもルドーラのためにであり、リムを労っているわけではない。
メディーナに言われたとおり、リムの体がどうすれば感じるのかというのを考え、どうすればより乱れさせることが出来るのか。
つまりリムを悦ばせるのではなく、ルドーラを悦ばせるためにラトはリムを責めているということになる。
だからリムの意思などラトには関係ない。
ただルドーラを悦ばせんがため、ラトはリムへ奉仕を続けていた。
「うあっ、うわぁぁっ!!お、おねえちゃ……ぁ!ダメッ!私、わたしまた熱、あつぅぅ!!」
そして、その奉仕によってリムの体は先ほどメディーナによって植え付けられた肉欲の熱がまたぶり返し、耐え難い疼きを呼び起こしていた。
「ふふ…、そう。それでいいんですよラトさん。
ラトさんの舌で、今この子の体は焼き焦げんばかりに燃え上がっていますわ。
もっともっとその子の体を昂ぶらせて、そのままあなたの手でこの子を絶頂に導いて上げなさい…」
「ふぁい……。んんんっ……!」
ラトは、メディーナに言われるままさらに舌をリムの奥深くへと伸ばし、ついには膣の奥の膜にまで届いてしまった。
これを貫きさらにその奥の子宮まで味わうことが出来たらどんなにいいだろうか、などとラトは一瞬考えてしまった。
が、それではここにリムを連れて来た意味がない。
リムの純潔をいただくのはルドーラ様であり自分ではない。ここで自分がリムの処女を奪うわけにはいかないのだ。
(リムがルドーラ様のしもべになったらたっぷり味あわせてもらうから、今は…)
多少後ろ髪を引かれるものはあるが、ラトは舌先にそれ以上力を入れることはなく
処女膜周りの肉襞をじゅるじゅると音を立てて舐めしゃぶり、同時に菊座の周りを人差し指でぐにぐにとほじくった。
「ひぎっ!やぁぁっおねえちゃん!!そんなにされたら、されたらあああぁぁっ!!」
先ほどまで散々おあずけを喰らっていたリムの体は、絶頂に導こうとするラトの奉仕に抗する事はとても出来なかった。
悲鳴と共にリムの体の奥底から溜まりに溜まった熱が出口を求めて込みあがり、一気に体の外に噴き出した。
「うあああぁ〜〜〜〜っ!!」
「んぶっ……」
他人の手による始めての絶頂、しかも焦らしに焦らされたことも合わさってその快感は今まで感じたこともないほどの大きなものであり
一瞬頭が真っ白になったリムは泡を吹きながらラトの顔に派手に潮を吹きかけてしまった。
「ひあぁ………あぁ!!
お、お姉ちゃん……ごめんなさいぃ……」
体内から異物を放出する爽快感に一瞬心を奪われ、すぐに正気に戻ったリムはべとべとになったラトの顔を見て
情けなさと申し訳なさから顔をくしゃくしゃに歪めて謝罪した。
が、ラトはリムに怒るどころかうっとりとした目線を向け、顔にこびり付いた淫液を長く伸ばした舌で丁寧にすくっていた。
「ダ、ダメッ!お姉ちゃん、それ汚い……」
「んふふ…、汚いわけあるものですか。『可愛い妹』の出したものなんだから、きちんと処理してあげないとねぇ……」
ラトはまるでリムが恥ずかしがる姿を愉しむかのようにわざと艶かしく舌を動かし、自分の顔だけでは飽きたらず
リムの太腿に飛んだ蜜もぴちゅぴちゅと音を立てて舐め取った。
「やぁぁ……やめてよぉ………」
もう抵抗する気力も萎えてしまったのか、リムはラトが太腿を吸う姿を弱々しく泣きながら見ていることしか出来なかった。
「うふふ…。すっかり大人しくなっちゃって。これでもう、この枷は必要ありませんね」
抵抗する意思を無くしたリムを見て、メディーナはリムを縛っている足かせと手かせの鍵をカチリと外した。
「えっ……きゃっ!」
それまでリムを縛り付けていた手首の抵抗がスッとなくなったかと思うと、リムの腰はガクン!と崩れ
ラトを巻き込みながらそのまま床に尻餅をついてしまった。
「ご、ごめん!お姉ちゃ…」
ラトを股に挟みこむような形になり慌ててリムは立ち上がろうとしたが、どうしたことかいくら腰に力を入れても体が立ち上がる気配を見せない。
「あ、あれ……?なんで?腰が、いうことをきかない……」
「クスクス…、それはそうよ。
今までイカせない程度にじっくりと愛してあげて、焦らしに焦らした後であんなに派手に気をやったんですもの。
とっくの昔に腰なんか抜けちゃっていますわよ」
自由にならない自分の体に戸惑うリムに、メディーナは手で口を抑えて笑いながら囁いた。
確かにこれなら拘束して自由を奪う必要はない。もうどうやっても逃げられはしないのだから。
そして、逃げられない状態になったということは、これから起こる事を避けることができないということになった。
「さあルドーラ様、準備は完了いたしてございます。
どうぞ、ごゆっくり御賞味くださいませ」
リムの股から顔を出し立ち上がったラトは、リムの後ろに回って抱きかかえると、面白そうに傍観していたルドーラを恭しく呼びつけた。
まるで、死刑執行を呼びかけるかのように。
続く
前の章へ