「ここがエレジタット…。噂には聞いていたけど、本当に何もないところなんだ……」
海路はるばる冥府兵団の本拠地・エレジタットにやってきたメイマイの外交官を務めているラトは、眼下に広がる岩だらけの絶景に息を呑んだ。
なにしろ本当に岩しかない。動物はおろか植物すらなく、生物の気配がまるで感じられない。
一説によればこのエレジタットという地には冥界の入口があり、そのため生けとし生ける者の存在を拒み続けていると言われているが、
それもまんざら嘘ではないような気もしてきた。
「なにしているんですかラトさん、早くついてきてくださいよぉ」
ものめずらしそうにあたりをキョロキョロとしているラトに遠くから声をかけてくるものがいる。ラトと一緒に船に乗り案内してきた冥府兵団の特使のエルティナだ。
「ああ、ごめんなさい」
ラトはぺこりと頭を下げると、先に進んでいたエルティナへ向けて駆け出していった。
「しっかし…、なんであんな子が、こんな鬱蒼とした国に仕え…ましてや特使なんてやってるのかな……」
自分だって充分歳若いのだが、ラトはいまいち納得できないでいた。この陰鬱とした国土とエルティナの雰囲気は、どうしても合わないと思ったからだ。
でも、そのことにいつまでもかまっているゆとりはない。
「まあ、他人のことを詮索しても仕方がないか」
なにしろラトはここに物見遊山で来たわけではない。ある意味、メイマイの今後を決めるやりとりをしに来たわけなのだ。
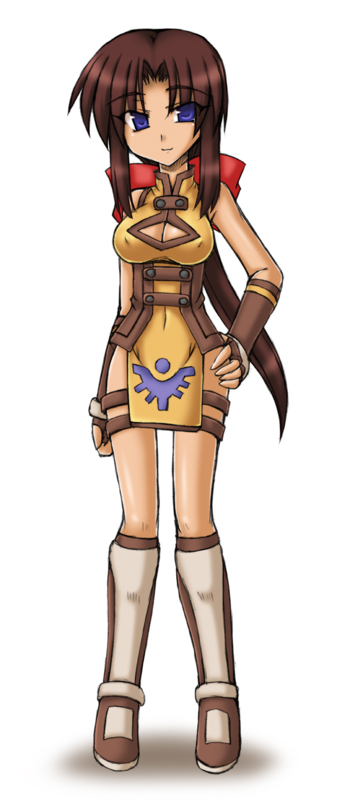
☆
それは今から大体二週間前、ネバーランドの東にある島に居を構えるメイマイ王国の港に一隻の船が停泊したことから始まった。
その船に乗っていた冥府兵団の特使であるエルティナは、メイマイの女王・ティナに軍事同盟を結ぶように言い付かってきたらしい。
「近頃、私たちの国の近隣のプリエスタが急速にその勢力を増しているのです。
そこでわが君主ルドーラは、あなた方と手を携えてプリエスタのこれ以上の版図の拡大を防ごうと考えて私を遣わしたのです」
まだ年若く見えるのに、エルティナは礼儀正しく丁寧な言葉づかいでティナへ応対していた。
その態度はメイマイの重臣達にも好印象を与え、またプリエスタの強国化はメイマイにも直接の脅威となるため
このエルティナの呼びかけに応じてもよいのではないかという意見が多数飛び交っていた。
だが、ティナとしてははいそうですかと同盟を締結するわけにもいかなかった。
エルティナがやってきたと言ったエレジタット一帯を治めているのは、ネバーランドでも暴威を振るう魔族の中でも
屈指の実力者で大魔王ジャネスの片腕とも言われたルドーラだ。
もしそんな国と同盟を組んだら、近隣の人間が治める国からどんな非難を受けるかわかったものではない。
基本的にネバーランドでは魔族=悪であり、その魔族と手を組むことで裏切り者呼ばわりされ、メイマイを護るために組んだ同盟が
逆にメイマイを戦禍に見舞うことになるかもしれない。
だがエルティナの言うことには、すでにプリエスタは隣国のハイラングールを攻め滅ぼし、
ハイラングールを治めていたダークエルフの兄妹を抹殺して国民は奴隷とされ侵略のための尖兵にされているらしい。
ティナとしては温厚とされているエルフがそんな非道な真似をするとはにわかに信じられなかったが、
同時に自分たちの種族以外には全く容赦はしないというエルフの種族特性も思い出した。
もしこれが本当なら、メイマイがプリエスタに攻略されたらメイマイの国民はまさに地獄の苦しみの中に落とされてしまうだろう。
そして、プリエスタとメイマイの距離は決して遠いものではない。
エレジタットとメイマイは、ちょうどプリエスタを挟み込む位置関係にあるので、同盟を結べばプリエスタに対し強力な牽制になる。
だが、魔族と同盟を結ぶことで魔族排斥を掲げている強国ロギオンや、傑物大蛇丸が治めるムロマチが牙を剥いてくる可能性はおおいにある。
また、ネバーランド本大陸から少し離れているメイマイは情報収集力があまり優れておらず、エルティナの持ってきた情報も
どこまでが本当なのか分かりかねるのが現実だった。
本当にエルティナの言ってることが真実なのか、メイマイを陥れるための罠ではないのか。
見た目、そんな策を労するようには見えなかったが、だからこそ油断を誘うという見かたもある。
「ラト、彼女の言っていることは本当かしら?」
ティナは古くからの友人であり、現在はメイマイの攻守の要である武将のラトに尋ねた。
彼女は身につけている宝玉の力で物事の正邪を判別する力を持っており、相手が嘘をついている場合はすぐに見抜くことが出来る。
「う〜ん、とりあえず嘘は言っていないみたいだけど…」
ラトの声は奥歯に物が挟まったみたいにはっきりとしない。
ラトの感覚ではエルティナは嘘を言っていないと判断している。
だが、エルティナの持つ気配がラトの心に一定の警戒心を抱かせており、素直に信じてはいけないとも感じているのだ。
「こっちを騙してなんの得があるかもわからないし…、正直なんとも言えないわ」
「そう……」
ラトで判断がつかないなら、誰に言ってもわからないだろう。
そうなると、代理とはいえ国主である自分の判断に委ねるしかない。
だが、ティナは決断を下せないでいた。
自分が判断を誤れば、決して強国ではないメイマイはあっという間に滅ぼされてしまう。
父から受け継いだこの故郷を、無残な姿に荒廃させてしまうのも自分の決断ひとつなのだ。
「……………」
俯いたまま一言も発しないティナを見かねたのか、ラトがティナの横に回ると肩を軽くぽんと叩いた。
「……しょうがないなぁ、ティナ。
じゃあ、私がこの目で見て確かめてくるよ」
「………え?」
「つまり、私が大陸まで行って実際に向こうの情勢を見てくる。
そうすれば、この先メイマイがどうすればいいかちゃんと判断できるでしょ」
要するに、ラトは単身海を渡ってエレジタットとプリエスタの情勢を見てくるというのだ。
情報網の薄いメイマイとしては、確かにそれは的確な判断かもしれない。
「それに、向こうの真意も聞いておきたいしね」
向こうとは勿論エレジタットのルドーラのことだ。
本当にただ同盟を結びたいだけなのか、それとも何か裏があるのか、本人に会わないと真実はわからないだろう。
「でも、それではいざとなったらあなたが……」
「大丈夫だって。私だって自分の体くらいは守れる。いざとなったらここまですぐに飛んで逃げてくるよ」
ラトの身を心配するティナに対し、ラトはあくまで軽い態度を崩さずにいた。
実際ラトもこれが自分が言うほど楽な仕事ではないとわかっている。最悪の場合も考慮しなくてはならないというのも頭では理解している。
だが、責任感の重いティナは何でもかんでも自分ひとりで背負い込む傾向がある。
以前からその傾向はあったが、国王代理となってからはそれがさらに顕著になっていた。
その負担を少しでも和らげることが出来れば…
ラトは親友と言う立場から、ティナにだけ重い責任を背負わすことを見過ごすことは出来なかったのだ。
「……わかったわ。でも、本当に気をつけてね。絶対の絶対よ」
「任せておきなさいって!」
こうして、ラトはエルティナに同盟を結ぶ下交渉という理由をつけて帰りの船に同行させて貰うことにした。
過去に何度かネバーランド大陸へは渡ってはいるが、エレジタットに行くのは初めてだ。
あまり良い噂は聞かないが、はじめて行く地ということでラトの心は少しだけだが期待に湧きあがっていた。
そんなラトを見るエルティナの瞳には、殆ど察知できないくらい微弱な邪な光が煌めいていた。
カツーン、カツーンとやけに足音が大きく響く。
エルティナに案内されてやってきたルドーラの居城は意外なほど小さいもので、メイマイの半分くらいの規模しかない。
もっとも、周りには街も何も無く岩だけの荒野が広がるのみなので大きさの割にはやたらと目立つ。
だがそれよりなにより、このルドーラの城には外と同じく、生きているものが殆どいなかった。
冥府兵団は一般兵士をほとんど魔法によって作られた人口生命体で補っているようで、城外にある施設で一律に管理されているらしく
城内のどこにも衛兵らしき姿は見えない。
「これって…、もしどこか攻め込んできたどうするの?」
ラトはもっともな疑問をエルティナにぶつけた。
「大丈夫です。ここエレジタットは険峻な地形ですから一気に大軍は入ってこれません。
そして、行軍に手間取っている間に魔法生物たちが展開して潰せるようになっていますから」
なるほど、このエレジタットはただでさえ半島の南端にあって攻め口が限定されている上に険しい地形が待っている。
しかも、他国にとってそこまでしてここの土地を奪うメリットが殆どない。岩だらけで農業もできず、人がいないので商業も絶望的。
つまり、この国が一個の城郭のようなものであり、うかつには攻められない&攻める意味がない構図になっているのだ。
ラトはなるほどと納得したが、そうなるとまた別の疑問が出てきた。
(だったら…、別にプリエスタに脅える必要はないんじゃないかなぁ)
エルティナはプリエスタの脅威に対抗するためにメイマイと同盟を結ぼうと言ってきた。それはエレジタットがプリエスタに攻め込まれるかもしれないというリスクを考えての措置だと考えていい。
だが、話を聞いた限りではプリエスタがエレジタットに攻めてくる可能性は限りなく低い。なのにメイマイと手を組みたがる理由は一体なんなのだろうか。
「ふふっ…、ルドーラ様にお会いになればすぐに分かりますよ」
そんなラトの心の中の疑問をまるで見透かしているように、エルティナは前を向いて歩きながら呟いた。
「!!」
ラトはエルティナの声に背筋が凍りつきそうになった。その声はそれまでの快活なエルティナからは想像もつかないほど薄ら寒く低いものだったのだ。
「………」
改めてラトは、自分が今魔族の城の中にたった一人でいるという現実を思い出した。
いざとなったら逃げ出す。ティナにはそう言いはなったが、正直それも出来るかどうか確信がもてなくなっていた。
できるなら、今すぐにでも横の窓から身を翻して逃げ出したい。
だが、前を歩くエルティナの気配からはまるで後ろに目でもついているみたいに隙が感じられず、
もし自分が逃げるそぶりを少しでも見せたならば即座にこの身を押さえつけられるのは明らかだった。
これは決して誇張でもなんでもない。
拳法を嗜むラトには、それまで全く感じられなかったエルティナから発せられる『気』が恐ろしいまでに強く感じられるようになっていた。
それはラトと互角か…あるいは凌駕するほどのものだ。これでは逃げる隙など出来はしない。
「さあラトさん……、ここがルドーラ様のおわすお部屋です……」
ラトに向け、口元を僅かに歪めて微笑んだエルティナは重そうな鉄製の扉を軋んだ音を立てて押し開いた……
☆
「ようこそ、メイマイの使者よ」
広さの割にはほんの数人の兵士がいるだけの部屋の中、不釣合いなほど大きい玉座に座っているルドーラを一目見ただけで、ラトの心に強烈な怖気が走った。
(こいつは、悪だ!)
ラトの直感は即座に判断した。
それは魔族だからだとかいうレベルのものではない。
ルドーラから発散させている気配そのものが非常に嫌な雰囲気をかもし出してきており、遠くにいるにもかかわらずラトの肌に鳥肌がたっている。
この男は存在しているだけで世界を混乱に陥れる。
この男と手を結んだら、メイマイは間違いなく大きな災厄に見舞われてしまう!
無意識に脚を一歩引いてしまったラトを見て、ルドーラは首を振って小さく笑った。
「どうかしましたかな可愛い使者よ、貴殿はここに何かを為すために来たのではありませんか?」
そう、ラトはここに同盟締結の下交渉を行うという名目でやってきていたのだ。
だが、その意思は既にラトにはない。冥府兵団と同盟を組んだら、早晩メイマイは地図から消えることになるだろう。
だからと言って、一言も言葉を交わさずに交渉を決裂させるわけにもいかない。
とりあえずルドーラの言い分を適当に聞いて、後は国に帰って検討するとかなんとか言ってしまえばある程度の面目は立つだろう。
「え、ええ…、そうでした……
ではルドーラ殿、あなたが私たちの国と結ぶことでプリエスタの拡大を防ぐとそちらのエルティナ殿は言われましたが、
正直ここの険阻な地形ならそれほど過敏になる必要はないと思われるのですが……」
とりあえずラトは先ほど浮かんだ疑問をぶつけてみた。同盟の第一前提があやふやな今、ルドーラの真意を正してみたかったのだ。
「なるほど……、歳と容姿に見合わず貴殿は良い見識をお持ちのようだ。では私もその明察に敬意を称し正直に話しましょう。
私が貴国と手を組みたい真の理由…
それは、プリエスタを貴国と挟み撃ちにして征服しようということなのですよ」
「……征服?!」
それはつまりエルティナがメイマイで話したことと全く逆の理由だと言える。
「そう、プリエスタの女王アゼレア…、あれを手に入れることが現在の私の一番の目的です。
その目的のため、貴国の力を借りたいというののですよ。
なに、私はプリエスタという土地に興味はありません。なんならメイマイに土地も民も差し上げても良いのです。
私はアゼレアを手に入れられればそれでよいのですから。
どうです、良い条件ではありませんか?」
つまり、ルドーラはプリエスタの女王アゼレア一人を手に入れるためにメイマイと手を結ぼうとしているのだ。
「なんで……?」
ラトには理解できなかった。たった一人の女性をかどわかすために国一つを征服しようだなんてどういう発想をしているのだろうか。
「アゼレアにはそれだけの価値があるということです。アゼレアを手に入れるためならば、幾百幾千の屍を築こうが問題ありません。
我が目的、神をも超える肉体を手に入れるためにはアゼレアが絶対に必要なのです」
「神を……超える肉体?!」
「はい。私は価値ある魂をわが魂と重ね、受け入れることでこの体を強化してきました。それこそ何百年という時を重ねて。
そして、ついにわが肉体を究極の高みにまで昂ぶらせる魂がこの世に現れました。
それが、アゼレアなのです」
神を超える肉体がどういうものかはラトには分からない。
ただ、ルドーラがそのことに非常に執着を持ち、そのためにアゼレアを異常に求めていることは理解できる。
なにしろ、今のルドーラの目の輝きは尋常ではない。それは願望どころではなく妄念の域にまで達している。
公に言っては憚られるが、間違いなくキ○ガイの目だ。
これは深く関わったら碌なことにならない。
「あ、ああ……。そうですか……
じゃあ、その旨を以って上のほうと今後のことを協議いたしますので、私はこれで……」
もうこれ以上ここにいてはいけない。
そう直感したラトは無礼を承知で生返事をして早々にここから立ち去ろうとした。
だが、扉の前にいる女兵士はラトの行く手を遮るかのように手に持った槍を扉の前に重ねた。
「なっ……ちょっとどけなさいよ!」
ラトはむきになって怒鳴ったが、藤色の髪をした女兵士は無言のままラトの行く手を遮っている。
「まあ少し待ちたまえ使者殿、私がどうやって神を超える肉体を手に入れようとしているか、知りたくはありませんか?」
「そ、そんなもの知りたくないわよ!!いいから帰して!帰してってば!!」
もう自分が国を代表しての使者だとか考えている余裕はない。
ラトは槍を弾き飛ばしてでも外に出ようとしたが、ぶん、と薙ぎ払われた槍にあっさりと体を持っていかれ、
玉座を降りてきたルドーラのところまで吹き飛ばされてしまった。
「そんな勿体無いことをしないほうがよろしい。せっかく神の秘密を教えてあげようというのに」
「神の秘密?!そんなものどうでもいいから、早くここから出して……キャッ!」
じりじりと歩いてくるルドーラからなおも逃げようとするラトに、背後から忍び寄ってきたエルティナがその体を羽交い絞めにしてきた。
「うふふっ、ダメですよラトさん。ここから逃げだそうなんて」
「なっ?!は、放して!放してぇ!!」
ラトはなんとかエルティナを振りほどこうともがくが、背後から掴まれているので力が思うように入らない上にエルティナの力が想像以上に強くびくともしない。
「…どうやら話を聞く気になったみたいですな。
私は、自らの肉体を高みに上らせるため、神が作り上げた超技術をこの身に課してきました。
その名は、『強制進化』といいます」
「き、強制、進化……?!」
それはラトが初めて聞く言葉だが、そのおどろおどろしい響きは聞くだけで背筋が凍っていく感じがしてくる。
「そう。
それは術者が施術者の魂を取り込むことで、その力を自分のものにできる素晴らしい技術です。
他者が持つ魔力、知識、経験など、あらゆるものがそれ一つで労せずして手に入れることが出来るのですよ。素晴らしいと思いませんか?」
何が素晴らしいものか。ラトは強制進化の持つ恐ろしさに身の毛がよだった。
それはつまり、他人の持つ力を奪い取って自分のものにするということだ。
確かにする側にとってはこれほど都合のいいものはないだろうが、される側にとっては自分が連綿と築き上げてきたものを一瞬で取られるはめになってしまう。
しかもこのルドーラは、何百年もそんな外道なことを積み重ねてきたと言っていた。
(こいつ……)
魔族だからとかいう訳でなく、ラトはこのルドーラに心底吐き気を覚えた。
こいつに比べたら、暗黒竜のほうが何百倍もましである。
ところが、ラトはルドーラをいまだ見誤っていた。
「ですが、それは私にとっては理由の一部にしか過ぎません。
私がアゼレアを求めるもう一つの理由は…、その肉体そのものです」
「肉体……?」
さっきルドーラは強制進化は魂を取り込む技術だと言い放った。
その理由からすると、肉体にはさほど意味はないと言えるのだが、ルドーラはその肉体すら求めているとしている。
「なぜなら、強制進化の真髄とは…
交合の果てに、至上の悦楽とともに力を取り込むからなのですよ」
「こっ……?!」
不意に予想もしなかった言葉を聞かされ、ラトの顔はたちまち耳まで真っ赤になってしまった。
「私は長年、色々な者と肌と魂を重ね合わせ、その力を手にしてきました。
強制進化の瞬間、私も私の体の下にいるものも歓喜の悲鳴を上げ、私は悦びとともにその者の魂を取り込み力を増してきたのですよ」
このときラトは気がついた。
自分を見るルドーラの目に先ほどから明らかな好色の色が浮かんでいたことに。
「よくよく見れば使者殿、貴殿からもなかなかに大きい力を感じますな……」
ルドーラの視線が、ラトの体を嘗め回すように移動している。まるで、ラトの肢体を吟味しているかのようだ。
絡み付いてくるかのようなねっとりとした視線に、ラトはゾクゾクと背筋を震わせた。
いや、考えてみれば会った時からルドーラに感じていた嫌な気配は、自分の体を狙われていることに無意識に嫌悪感を生じていたからなのかもしれない。
「ひっ!や、やだぁぁ!!」
「怖がらなくていいんだよラトさん。ルドーラ様にされるのって、すっごく気持ちいいんだから……」
ラトの後ろで薄笑いを浮かべるエルティナの体に、赤黒い痣のような紋章が浮かんできている。
暗く光る虹彩もエメラルドグリーンから徐々に血のような真っ赤な色に変わり、髪の間からは耳がにゅうっと顔を出し始めていた。
「私も、ルドーラ様にされるまでは泣いて嫌がったけれど、一回ルドーラ様に強制進化される気持ちよさを知っちゃったら、
もうルドーラ様なしではいられない体になっちゃったし…うふふ」
ルドーラとの睦み事を思い出しているのかエルティナの顔はどんよりと蕩けている。心なしか、下腹部が当っているところから服越しに湿り気の感じる。
「彼女…エルティナは私がふらりとゴルデンのほうに足を伸ばした時に手に入れました。
その身に似合わずなかなかに素晴らしい輝きの魂を感じたので我慢できなくなりまして……つい味わってしまったのですよ。
強制進化とは互いの魂を重ね合わせる儀式。私は相手の力を貰いますが、その代わりに私は相手に私の魂の一部を分け与えます。
そうすることで、私に強制進化を施された者は言わば私の分身のようなものとなり、忠実なしもべとなるのです」
「はぁい…。あの時からもう私はルドーラ様のことしか考えられなくなっちゃってぇ…、
こうしてルドーラ様の手足になってお役にたとうといっつも努力しているんですよぉ」
ということは、エルティナはルドーラに自分の意思で仕えているのではなく、ルドーラによって施された
強制進化でその心を支配されている状態と言っていい状態なのだろう。
「ひ、ひどい……。なんてことを……」
ラトはルドーラの外道ぶりに思わず憤ってしまったが、その次に恐ろしいことに思い至った。
ルドーラに強制進化されたなれの果てが後ろにいるエルティナならば、もし自分もルドーラに強制進化を受けてしまったら
エルティナのようになってしまうということになる。
自分の意思も何もかも関係なく、ただただルドーラに奉仕することに喜びを感じる肉人形に…
「さあ貴殿にも味あわせてあげましょう。この世の最高の悦楽を……」
ルドーラの手が服を破り裂こうと羽交い絞めにされているラトに伸びてくる。これに掴まれたら、もう逃げることは出来ない!
「い、いやああぁぁっ!!」
なんとかエルティナを振りほどこうと、ラトはメチャクチャに体を揺すって暴れまわった。
すると、偶然のタイミングでエルティナがラトを押さえつけようと体を前に倒した時と、ラトが体をかがめた瞬間がちょうど一致した。
「えっ?きゃぁっ!」
「?!うおっ!!」
エルティナは踏ん張りがきかずにたまらず体を前に投げ出され、体を屈めてきたルドーラと正面から鉢合わせになってしまった。
どかぁん!と痛そうな音を立ててルドーラはエルティナを巻き込んで後頭部からぶっ倒れてしまった。
つまり、今ラトの体を縛るものはなにもない。
「!!よしっ!」
今こそ脱出の好機と見たラトは素早く立ち上がって入口の扉目掛けて走り出した。そこには先ほど道を塞いできた衛兵が待ち構えていたが、もうラトには衛兵に手を出すことに躊躇する理由はない。
「遥かなる混沌の時代より、世界を創りし純粋なる竜よ、その大いなる力を牙に変え解き放て!ロースファイヤー!!」
ラトが懐からぱっと取り出した宝玉から紅蓮の炎を纏った竜が飛び出し、扉目掛けて突っ込んでいった。
当れば扉など一撃で吹き飛ぶ上、すぐ横にいる衛兵も無事ではすまないだろう。
バガァァン!!
ロースファイヤーの直撃を直撃を受けた扉は予想通り木っ端微塵に粉砕し、向こうの壁まで壊して大穴を穿っていた。
横にいたはずの衛兵は巻き添えを食らったのかどこにもいない。
「やたっ!」
脱出への道がようやく開け、ラトはわき目も振らずに壊れた扉目掛けて駆け出した。もう自分を妨害するものはいない…
後は一刻も早くメイマイに戻り、冥府兵団の危険性を教えなくてはいけない。
(はやく…早くこの事をティナに!)
ラトの頭には自分は助かったという安堵感で僅かながら緊張が解けていた。そのため、周りへの警戒心もほんの少しだが緩まってしまっていた。
その時、不意にラトの腹にどすんと鈍い痛みが走った。
「……え?」
何が起こったのかわからないラトが視線を下に移すと、前から伸びてきた槍の柄が深々とラトの鳩尾にめり込んでいる。
それを自覚するにつれて息はどんどん詰っていき、腹の奥から熱いものがこみ上げてきた。
「………っ?!がはぁっ!!」
まるで腹を貫かれたような痛みにラトは血反吐を吐き、その場にくたくたと崩れ落ちてしまった。
早く逃げないとと、と頭は警鐘を鳴らしまくっている。が、ラトの下半身はラトの頭の言うことをまったく聞かず腰を上げることすら拒否している。
「はは…、ここから逃げようなんて甘いんだよ、ラト」
うずくまったラトの眼前にいたのは、ロースファイヤーで吹き飛ばされたはずの女兵士だった。
「なっ……、あの距離で…ロースファイヤーを避けたっていうの……?」
あれはほとんど不意打ちのタイミングだった。どう考えても避ける隙はなかったはずだ。
だが、衛兵はコゲ一つ負わずに悠然と立っている。ラトとしては信じられない思いだ。
「絶対に避けられないタイミングで撃ったはずなのに……」
「何言ってるんだい。あそこでラトが攻撃を仕掛けてくるなんてのは見え見えじゃないか。
宝玉出した時点でもう避け始めているし、後は素早くラトの側面に回り込めば…結果はみての通り」
衛兵は得意満面に種明かしをしているが、その一言一句にラトは引っかかるものを感じた。
この女兵士は、まるで自分のことをなにもかもお見通しだと言わんばかりだが、何故こうも自分のことを知っているのだろうか。
過去にネバーランドに来た時にあったことでもあるのか?でもだからと言って、自分の攻撃のクセの事まで知っている人間はそうはいない。
満足に呼吸ができずいまいち働かない頭を必死に回しているラトに、女兵士は呆れたように首をすくめた。
「なんだ、僕のことを忘れちゃってたのかい?薄情だなぁ。
ほら、僕の顔をよぉ〜〜く見てみなよ」
さっきのエルティナと同じくルドーラの下僕の刻印が全身に浮かんできている女兵士は、ラトの顔を無理矢理自分の方へと向けた。
ラトの視界いっぱいにに女兵士の顔が入ってくる。が、ラトにはそれが誰かどうしても追い出せない。
(いったい……誰なの?こんな女の子、私会った事もない……)
以前ネバーランドに武者修行に来た時にはこんな女の子と打ち合ったことはない。
暗黒竜アビスフィアーが復活して暴れた時も、この女の子と会った覚えはない。
後は、本当に昔の昔。10年以上も前のこと。
ラトが6歳の頃、嵌っていたモンスターコンプリート、通称モンコンの大会のためにネバーランドに来た時があった。
でも、あの時もこんな女の子にあった覚えはない。
(でも……)
それによく似た『男の子』には会った事がある。彼女と同じ藤色の髪をしていた男の子。
そう言えば、顔形もよく似ている。いや、よく似ているどころか瓜二つ。どころではなく全く同じ……
「え……?まさか……あなた……、シフォン………なの?!」
まさかという思いでラトはその名を口に出した。すると、女兵士はクスリと柔和に、だがどことなく馬鹿にしたように微笑んだ。
「あぁ、覚えていてくれたんだ。
そうだよ、昔一緒にモンコンしていたシフォンだよ。懐かしいねぇラト」
「う、嘘よ……
だって、だってシフォンは男の子よ?!でも、でもあなたはどう見ても女じゃないの!!」
確かにその自己主張しすぎる大きな胸。ぎゅっとくびれた腰。まろみを帯びた尻はどこをどう見ても女性のものだ。
ひょっとしたら自分が昔からシフォンのことを男の子だと勘違いしていたのかもという発想もよぎったが、どう考えてもありえないことなので即座に否定した。
「うん。確かに以前は僕は男だった。けれど、ルドーラ様のおかげで女にしてもらったんだよぉ…」
ルドーラの名前を出したシフォンは心底嬉しそうに体をもじもじとくねらせている。これは先ほどのエルティナと同じであり、シフォンがルドーラの強制進化の犠牲にされてしまったことを物語っているものだ。
「なんで……なんでそんな……」
「ああ、そやつはジャネスを倒した強者だと聞いたから、エルティナを遣わせて連れてきたのですよ。女に変えたのは単なる趣味ですが」
「うふふ、実はシフォンって私の幼馴染なの。だから簡単に騙されてくれたわ。
傑作だったのよ、体が女の子にだんだん変わっていく時のシフォンのビックリした顔。
そして、ルドーラ様に抱かれて、女の子になったばかりなのに肉欲の虜になって行く姿…、思い出しただけで濡れちゃいそう…」
愕然とするラトに立ち上がったルドーラとエルティナが話し掛けてきた。
そしてそれはこの瞬間、ラトがここから逃げ出す機会が完全に失われたことも意味していた。
「ですが、とんだ見込み違いでした。幾許かの人間よりは遥かにましでしたが、とてもジャネスを倒すほどの強さは持ち合わせない魂でしたね」
「あぁん、言わないでくださいルドーラ様ぁ。あれは僕の力ではなく、僕の持っていた剣の力なんですから。
それに今、僕はとっても幸せなんです。勇者って重苦しい肩書きから解放されて、一人の女としてルドーラ様にお仕えできることができるんですからぁ」
確かにシフォンの表情はやや壊れてはいるものの、限りない開放感と幸福感で彩られている。
それはまだ勇者ともてはやされていた頃の陰鬱なシフォンを知る人間からしたら想像も出来ないことだ。
そう考えれば、シフォンの言っていることは決して人前では言うことの出来なかった本音なのであろう。
だが、ラトは幼い頃の明るいシフォンしか知らないのでシフォンの言っていることはさっぱり理解できない。
むしろ、ルドーラの洗脳によって言わされているようにしか聞こえなかった。
「ちょっ、しっかりしてよシフォン!こんな変態魔族の言うことになんか惑わされないで!!」
「変態……?ラト、ルドーラ様のことを悪く言うのはやめてくれないかな……」
ルドーラを侮辱されたからか、シフォンは顔を怒りに曇らせてをラトの服の襟を掴み、そのまま下にビリッと引き裂いた。
「キャアァッ!なにするのよシフォン……!」
「なにって……。これからラトはルドーラ様に捧げられるんだから服なんか邪魔だろ?手間を省いてあげたんだよ」
「!!」
そうだった。自分はルドーラに襲われようとしていたんだ!
しかしラトが自分の危機を思い出したのはあまりにも遅すぎた。既にラトの周りはシフォン、エルティナ、ルドーラによって包囲され、例え体調が万全であっても逃げることは不可能であったろう。
「い、いやっ…」
ラトは慌てて立ち上がろうとしたが、今度は左右からシフォンとエルティナに掴みかかられ、その両腕をがっちりと掴まれてしまった。
「や、やだっ!放して……」
「そうはいかないんだよ、ラト」
「今度は逃がさないわよ。さあ、こんな邪魔な布っきれは取っちゃいましょうね」
エルティナの手がラトのパンツに伸び、ぐいっと引きちぎってしまった。
ルドーラの前に、下半身が露わになったラトがその姿を晒されている。
「ふふ…、なかなか昂ぶらせてくれるではないですか。
では、その体の中に流れる力をいただきましょうかね」
ルドーラは自分の逸物を晒し、ラト目掛けて腰を屈めてくる。
その股間にそそり立つグロテスクさと、それが自分に埋まることへの嫌悪感にラトの顔は恐怖に引きつっていた。
「いやあぁ――っ!!やだっやめて助けて!!ティナ、ティナァ、助けてよぉ――っ!!」
自分のあまりにも楽観的だった見通しが、今の絶望的な事態をひき起こしてしまった。自業自得といえばそれでおしまいだが、あまりにも残酷に過ぎる。
「さあ、私を満足させてくれたまえ!」
ルドーラのモノがみちみちと音を立てて、ラトの秘裂をこじ開け中へ中へと捻じ込まれていく。
「ひっ?!
いだっ!やめでぇ……」
ラトの股間から、処女の証である破瓜の血がとろとろと零れ落ちてきている。
何の前戯もなしにいきなり突っ込まれたそれからは体を引き裂くような強烈な痛みしか感じられなかった。
「いたい!いたい!いたぁい!!
こんなのいやだぁ!お願いだから抜いて!たすけてぇ!!」
「…いいぞ。その声、そして内に篭る力……。貴殿は内にガジュウを宿しているのか……
これはまたとない収穫!望外の悦び!これだから強制進化は止められぬわ!!」
ガジュウとは大地の力の総称であり、ラトはガジュウの力を宝玉を介して扱うことが出来る。先ほど放ったロースファイヤーもガジュウを用いての技だ。
だが、誰しもがガジュウを扱えるわけではなく、素養、資質、そしてたゆまぬ努力の果てにようやくその力を奮うことが出来るようになるのだ。
そして、研鑚され鍛え上げられた力はルドーラにとっては無上の悦びをもたらすものでもあった。
強制進化の際に吸い上げる力は大きければ大きいほど、術者に強烈な悦びを与えてくるのだ。
ルドーラはラトの内に秘められた力の強さに歓喜し、その昂ぶりはラトの中に突っ込まれた肉棒へと伝わりその大きさと堅さをさらに増していった。
それはルドーラにはこの上ない喜悦をもたらしたが、初めて男を受け入れたラトにとっては痛みがさらに酷くなる結果しかもたらしてこなかった。
「あああぁぁぁああぁ!!いたぁっ、中で擦れてぇ……!もういやぁぁ!!!」
抽送されるたびに頭に割れそうな痛みがガンガンと響いてくる。
ずちゅっ、ずちゅっと粘膜が擦れあう音がするたびに焼け付くような痛みが下半身に走ってくる。
暴れて抵抗しようとしても手足をシフォンとエルティナに押さえつけられ、ガジュウを解放する宝玉も手に取ることが出来ない。
「あぁ…ラトったら凄く痛そうだねぇ……」
「私たちも最初はそうだったわよね。ルドーラ様のオチンポ挿されて、痛い痛いって泣き叫んだもの。でもね……」
これからラトは歓喜に泣き叫んでルドーラ様のものになる。それを知っている二人は興奮に顔を赤らめながらラトをじっと眺めていた。
「ふふ…、やはりなにもせずいきなり情交に及ぶのは苦痛ですか。申し訳ありません」
口では謝罪の言葉を出してはいるが、ルドーラは腰の動きは全く緩めずラトの中を抉り続けている。
ラトのほうはあまりの痛さと激しさにもはや悲鳴すら上げることも出来ず、陸に上がった魚のように口をパクパクとさせながら、
ルドーラの腰の動きのままに体を揺すらせていた。
「ああ、もう声を出すことも出来ませんか。では次の段階に行きましょうか。
今まではただの男女の睦みあい。これからが強制進化の醍醐味ですよ」
いまだ激しく腰を揺するルドーラの全身にある計7つの目が、不意に赤く輝き始めた。
その光はやがてルドーラの全身を覆い始め、腰の繋がっているところを介してラトのほうへも伝播していく。
そして、茫然自失しているラトの瞳がボゥッと輝いた時、変化は起こった。
「あ……え?」
それまで痛みしか感じなかった下腹部に、突然甘い疼きが襲ってきた。
その疼きはラトの耐え難い痛みを一瞬にして消し飛ばし、脳内を快楽で染め上げてしまった。
「な、なにこ、れえええぇぇぇっ!!」
痛みに麻痺していた心に突然なだれ込んできた暴力的な快感に、心の準備などしていなかったラトは
受け流すことも受け入れることも出来ずまともに感じる羽目になってしまった。
その快感は性の経験が全くないラトの体を熟練の情婦のように快楽を受け入れる肉体に変え、
性の知識を持たない脳にどこをどうすれば一番感じるかという情報を入力させてきた。
「き、きもっ!気持ちいいぃ!やだこれなんで私、わたしぃぃ!!」
自分の体に何が起こったのか全然理解できないラトだったが、その体に入力された性の知識が無意識に自分の体が最も悦ぶ体位を選択し、
ルドーラの巨大な逸物をこねくりまわしていた。
それがまた文字通り腰が抜けそうなほど気持ちいい。
「変よっ!私、こんなの知らない!知らないのにああぁぁ気持ちいいのぉぉっ!!」
戸惑いながら腰を動かすラトの顔には、先ほどは全く見えなかった歓喜の笑みが浮かんでおり、流している涙も痛みから悦びへと変わっていた。
「な、なにをしたのルドーラ……ァ!!こんなの、わやしじゃ、な……あああぁ!!」
「ふふふっ、戸惑っていますね。自分が知らないことを体が、心が覚えている。
まるで、自分の心と体が誰か他人の知識を手に入れたみたいに……
「そうです。これが魂を重ねあうということですよ!」
先ほど、ルドーラは強制進化は魂を重ね合わせる儀式だと言っていた。
つまり、ルドーラはラトの魂と自分の魂を重ねることでラトの力を吸収しようと目論んだが、その副作用としてルドーラが知っている知識…
性の知識がラトの心と体に流れ込んできてしまったのだ。
もっとも、これは半ば意図的にルドーラがラトの体に流したようにも見受けられる。
ラトが感じた快感を魂を重ね合わせているルドーラも感じ、それによってより昂ぶったルドーラの魂がまたラトの魂も昂ぶらせより
強い快感となってラトの心身を侵してくる。
そしてそれがさらにルドーラを昂ぶらせ、それがまたラトを…まさに快感の共鳴状態。
これこそ、ルドーラが語った『至上の悦楽』というものなのだろう。
天井知らずに高まる快感はルドーラにとっては慣れたものだが、これが初めての性交であるラトにはあまりにも刺激が強烈過ぎた。
「うはああああぁ!!きもち、きもひいいよぉ!私のあそこ、ぐちゅぐちゅしてるぅう!!
へんになるぅ!こわれ、こわれひゃうよぉぉ!!」
自分の体の中に膨れ上がる強烈な快感を制御しきれなくなったラトは、汗と涙と涎を撒き散らしながら狂ったように腰を振り続けていた。
「ははははっ!!これは凄い!これほどのガジュウを従えていたのですか!素晴らしい!これが私のものになるのですか!!
どうですか使者殿!強制進化の味、十分に堪能していますかな?!」
「ああぁっ!!す、すごいですぅ!!もう、もうきもちよすぎてなにもかんがえられなぁ……
うわはぁぁ〜〜〜〜っ!!いいっ!そのゴリッとしたのきもひいぃ〜〜〜!」
完全に抵抗する心を失ったラトは、ルドーラに向けて壊れかけた笑みを向け全身を蝕む快楽に溺れきっている。
もう逃げる意思もないだろうと確信したシフォンとエルティナがラトの手足を解放すると、ラトはあっという間に両足をルドーラの腰に絡め、
両手をルドーラの肩に回して力いっぱい抱きしめてきた。
「エルティナ、これでラトもルドーラ様の虜だね」
「うふふっ、また一人、ルドーラ様のしもべが生まれるのね」
シフォンとエルティナが見つめる中、ルドーラとの強制進化に夢中になっているラトの体のところどころがポゥ、ポゥと光り輝き始めた。
それは次第にシフォンたちの体に浮き出ている紋章の形となり、ラトの体と心を侵食していく。
ルドーラの魂と重なり合ったラトの魂の色が、元々のラトとしての色からルドーラの色と溶けて混ざり合い、全く新しい色へと変わりつつある。
「あっ?!ひっ?!
なにこれなにこれぇ!わたしが、わらひがまざっちゃう!まざって、なくなっひゃうぅ!!
でも、でもすごぉい!!わたしがかわる!かわっていくのよぉ!!」
自分が自分ではなくなるという異様な感覚。しかしそれは決して不快なものではない。
心の中から全く新しいものに変えられるというのが、ラトにとっては素晴らしく爽快なものに感じられていた。
「それが私のモノになるということです。今、あなたの魂は私の力を取り込み全く新しいものになりつつあります。
メイマイのラトという人間はなくなり、私の忠実しもべとして新しく生まれ変わるのですよ」
(うまれ…かわ……?!)
あまりにも強烈な快感で飛びつつある意識の中にルドーラの言葉がひどくはっきりと聞こえてくる。
ルドーラの魂と溶け合ったラトの魂にはそれは絶対的な響きとして伝わり、ルドーラに対する忠誠心が刻み込まれていった。
「あ……ああ!!
そうですぅ!ラトは、ラトはルドーラ……さまのものですぅ!ルドーラ様のしもべなんですぅ!!
この体も心も、みぃんなみぃ〜んな、ルドーラ様のものなんです!ルドーラ様の、ものなんですぅぅ!」
ラトはまるで自分に言い聞かせるように自分のことをルドーラのものだと連呼し続けた。
そして、連呼する毎に体に浮かぶルドーラのしもべの紋章もその濃さを増していった。
「ふふふ、いい感じに染まってきましたね。では、そろそろ締めといきましょうか。
これであなたは、完全に私のものになるのですよ!」
それまでも激しく腰を動かしていたルドーラだったが、これが止めとばかりにより深く腰を打ち付けて来た。
そして、その瞬間らとの膣内にルドーラの力がたっぷりと含まれた精液がはちきそうなほど多量に注ぎ込まれてきた。
「ひぎっ?!ああぁ――――っ!!」
子宮の奥の奥まで熱い迸りを受け、すでに頭がパンクしかけていたラトはあっというまに絶頂に達し、ルドーラに抱きついたままかくんと頭を倒した。
「は、はひ……。きもち、い……」
殆どうわ言のようにつぶやくラトの体にはくっきりとルドーラの紋章が浮かび、快楽に霞む瞳も元の瑠璃色から血のような赤色に変わっている。
耳も横ににょっきりと伸び、その変化した姿はシフォンやエルティナとまったく同じものであった。
「ラト、これであなたも私の忠実なしもべとなりました。これからはアゼレア奪取の為、役立ってもらいますよ」
達した余韻でいまだに荒い息を吐き続けているラトだったが、ルドーラのほうへと顔を向け、こっくりと頷いた。
「は、はいぃ……。お任せください………。ルドーラ様………」
赤く染まったラトの虹彩は、ルドーラに奉仕し従うことができることへの悦びで熱く濡れていた。
☆
「ではエレジタットとは同盟を結んだ方がいいというのがあなたの出した結論なのね?」
ティナは、メイマイに戻ってきたラトから大陸での経過報告と、今後進むべき道を聞かされていた。
「ええ。大陸でもプリエスタの勢力拡大はかなり警戒されている。このままだと、きっとメイマイまでその手は伸びてくる。
それを防ぐためにもエレジタットとは手を組んだほうがいいというのが私の意見よ」
たとえロギオンを敵にまわすことがあっても、そこまでラトはティナに言い切っていた。
「………分かったわ。
プリエスタのほうが危険だというあなたの見識を信じる。今から重臣たちと会議を開いて、エレジタットとの同盟を結ぶ方向で話を進めてくるわ。
その時は……、またあなたをエレジタットに向わす事になると思うけど……いいわね?」
「勿論!ティナの…いいえ、メイマイのためだもの。苦労は厭わないよ」
「ありがとう…、ラト」
親友の心遣いが身に染みたのか、ティナはうっすらと嬉し涙を浮かべながら部屋を後にしていった。
その後姿を、ラトは目を細めながら薄ら笑いを浮かべて見送った。
「うふふ…これで予定通り。
あとはティナにプリエスタを攻めるように言いくるめれば、プリエスタを挟み撃ちにすることが出来る。
そうすれば、ルドーラ様が求めるアゼレアも簡単に手にすることが出来る……」
そうすれば、ルドーラ様も大層お喜びになるだろう。
「ティナ……、その時はついでにあなたもルドーラ様に捧げてあげる。ルドーラ様のものになる悦びを、あなたにも味合わせてあげるよ」
あの清楚なティナがルドーラに抱かれ、人目も気にせず乱れる姿を想像しただけでラトの心の奥がキュウッと締まってくる。
「そうだ、ルドーラ様のところに戻る時、リムもいっしょに連れて行こうっと。
リムもルドーラ様のしもべにしておけば、メイマイでの工作ももっとしやすくなるだろうしね、クフフッ」
大事な義妹のリムを罠にかけることにも全く躊躇しない。
身も心もルドーラの下僕へと堕ちたラトは、これからいかにメイマイを戦乱の道に持っていこうかと、邪悪な思索に暮れていた。
続く